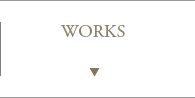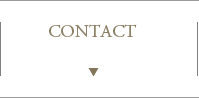その白い一体の石膏像こそが、二田原英二の原点であった。
両手で右膝をすっぽりと抱きかかえ、顔をややうつむき加減にした女性のそのまろみを帯びた体躯はまるで母の胎内に宿る胎児のようである。
手足はやがて身体の一部となり、次第に溶け合ってゆく様は柔らかな卵形を髣髴させ、見るものを安らかな境地に導いてゆく。
静かに無心に目を閉じる人体を通して、彼は何を語ろうとしていたのだろうか。
1956年、大学卒業後、副手時代の二田原が初めて取り組んだのがこの作品である。
おそらく彫刻を通して「人間の存在」を永久命題とした最初の作品でもあった。
そしてこの作品を契機に彼は彫刻とともに歩むことになる。本人の言をかりるならば「お前とともに歩もう。命の果てまで。
わたしはおまえであり、おまえはわたしなのだ」ということになろうか。
真夏の暑い研究室で何度も試行錯誤を繰り返しながら、彼はその形状の中に「かたまり=塊」が持つエネルギーのようなものをみたのだ。
内在するエネルギーは、やがてある一点から破壊的ともいえる力で爆発を起こしあらゆるものへと変容してゆく。
それはまさしく無意識における若い彼の有り余るエネルギーのメタファー(暗喩)であったかもしれない。
一見、静寂にみえる像の中には、はかりしれないエネルギーが沸々と滾っている。
ただ一つのゼロ点に集中する力は、彫刻という造形言語を通して外部に向かう巨大な力になりえることを彼は確かに感じていた。
そして、それこそがまさに二田原英二の作品すべてに通ずる原点であるといえよう。
「作品の題名は?」と問うと、しばらくして「『 夢 』・・・かな」という答えが返ってきた。
今なお、彼の創作に全くのブレはない。