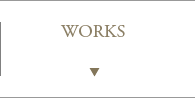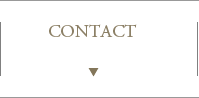joan随想記
これが今から十年ばかり前に、見知らぬ婦人 Y.N の私に宛てた手紙の全文です。
お察しの様に婦人は四十年程昔、二十歳で此の世を去った兄の最後に愛した女性です。恐らく生涯でただ一人の・・その愛は今もなお彼女の中に静かに住まい、ひっそりと息ずいているのです。
婦人は戦後数年たって陶芸家と結婚し一男一女をもうけ、今は奈良の近くの木津に暮らしています。ある機会に長男と会ったことがありました。なかなか闊達で明るい青年でした。その気質のように古代地中海世界に強く魅かれ程なく留学生としてイタリアへ出発して行きました。どこかで貴兄と合い通ずる薫りの様な何かを感じていました。物心付く頃から母に連れられてよく大和や京の寺社仏閣に足を運んだそうです。屈託なく笑いながら、“父に反対されたのですが、古代エトルリアの陶棺夫婦像やアポロンの陶像の図版を開きながら、”いずれ僕は親父の窯を継ぐことにならのだ、と言ってうまく説得したのですよ“と私に語ってくれたのがとても印象的でした。この若者については、又、別の機会にどうしても触れねばならなくなるでしょう。
所で,件の兄の残した「優艶」を読んで頂きましょう。
―――――――――――――
Ⅲ.
陽が傾き春の日が暮れようとしていた。謝肉祭というのに街じゅうが静まりかえっていた。第一このピアッツエッタからサン・マルコ広場を見渡した限りでも人影らしい気配すらない。見知らぬ或る男からの連絡を受けて僕はわざわざ旅先のシエナからこのヴェネツィアへやって来た。今日の夕方、ゴンドラの船着き場の渚に椅子をだして待っていてほしいいと言うのだ。つまりサン・マルコ広場野の有翼の獅子像と聖テオドーロの像を戴くあの花崗岩の二本の円柱を見上げながらだ。
数日前のことである。シエナの朝の心地よい陽射しが貝殻状のカンポ広場にプ
ッブリコ宮殿の影を緩やかに描いていた時刻、僕が、あくびをしながら碧い空を仰いでいると八つになるかならぬかの少女が、それも見知らぬ可愛い少女が貝殻の広場を斜めに真っ直ぐ歩いて来て小さな白い紙きれを僕に手渡した。“おじさん、これメッセージよ”思いなし傾げた顔に陽が射して華奢な肌が大理石の様に輝いた。額で透けるように小さな渦を巻いていている細い金髪のせいだろう。
“有難う、誰かに頼まれて?”“ええ、ほら、あそこにバールが見えるでしょ、素敵なおじ様に頼まれたの、ベージュのコートを着た方よ”、少女はあどけなく淡い緑色の瞳を見開いて広場の端の方に向かって顎をしゃくると、不思議そうに僕を見上げた。それは、どこか見覚えがあるわ、といった表情であった。僕は、バールの方を確かめたがそれらしい人影は見当たらなかった。多分、少女が僕に紙きれを手渡すのを見届けると急いでバールを後にしたに違いない。『若しよろしければ、謝肉祭の最後の日の夕刻、ヴェネチアでお会いしたいのですが、サン・マルコ広場のゴンドラの船着場で、貴方の古き友 G.C より、友情を込めて』と、二つ折の紙に流麗な走り書きで記してあった。誰だろう。しばらく特徴のあるG.C のイニシャルを手掛かりに記憶の糸をたぐるのだが、どんな顔も浮かび上がってこない。幾度か訪れたヴェネチアへはいつも独りだったし、いきずりに知り合った女であるはずもない。かなり風変りな誘いだとはおもうが、さりとて何か品よく仕掛けられたわなだとか巧みな企てとも思えない。
僕は思案に暮れ、ただぼんやりと広場に這う建物の影を目で追った。結局は今日一日の気分次第ということになるだろう。或いは、古代エトルリアの鳥占いよろしく北の空を見上げながら、飛ぶ鳥の行く方で決めることになるだろう。気が付くと淡い金髪の少女は居なくなっていた。もはやG.C が誰であるのか知る手だてはない。
先程まで貝殻の広場の外縁まで延びていたのっぽのマンジャの塔の影が短くなっていた。褐色の建物に囲まれ、なだらかな傾斜の広場が昼下がりの陽気で温められる頃、行きかう人の動きは緩慢となって遂には歩みを停めてしまう。そして思い思いに石畳に腰をおろし背をこごめ、こうして広場は極上の憩いの場になっていく。
僕は何故か、広場の片隅のバールに陣取り、本を手にしたり書き物をしながら、時の流れに形を変え変容していくマンジャの塔の影を日長一日追うのがすきで、ほとんどそのためにこのシエナに滞在しているのだと言ってもおかしくはなかった。山上の城郭の街が間昼間、茶褐色の露地や壁の陰影を濃くする時刻、人影の停まった外れのテラスに立って波打つオリーヴ・グリーンの起伏を見下ろしていると、それだけで幸せになって行く。どんな言葉もいらない。ただ幸せなのだ。
過ぎ行く今に自足するのがどんなに素晴らしいことか、説明するのは難しい。どんな言葉も,否、人までも、しまいには曖昧模孤となって消えていく。全ては大きなため息でしかないのだ。
僕はかってこの街にシモーネ・マルティーニの優美さやドウッチオーの荘重さに憬れて遥々、異国からやって来た。古ぼけた美術書の色刷りを繰り返し眺めているうちに、憧れは本物になっていた。初めて見るマエスタ「王座の聖母」を前にした時、美術書が解説する「精神の集中、荘重と抒情」という言葉がようやく真実の響きとなったのを覚えている。素晴らしいことだった。言葉が肉付けされ、肉付けされた言葉が僕のなかで「生」を生きはじめている。一つの『生の形式が』が誕生していたのだ。
僕はいつの間にかパンタネト通りの外れのピスピーニの門に近いホテルに戻っていた。かなり想いに耽っていたらしく何処をどう歩いて来たのか定かでない。ホテルの白髭を両頬に蓄えた老いた小太りの玄関番がキーを差し出しながら“旦那様、メッセージです。お知り合いの方とか申されて電話がありましてね・・”と伝言用紙を差し出した。『先程は急いでいましたので失礼しました。ゴンドラの船着き場では椅子に座って厚手のジャケットを念の為、ヴェネチアの夕暮れはかなり冷えますので・・・、私は多分、仮面を付けて参ります。風変りな趣向と思われるでしょうが、私としましてもひさしぶりのヴェネチアです。それに何よりも貴方様とのお話を楽しみにしております。貴方の古き友 G・C より』、又してもあの男からの連絡なのだ。そして如何にもヴェネチアらしい風変りな・・、僕の決心はこれで殆んど決まった様なものだ。若しかしたら,こうした仮面舞台の場面ででもあるような出会いの機会をひそかに待ち望んでいたのかもしれない。
僕の心は昂ぶっていた。窓を開けるとトスカーナの丘陵がオリーヴと葡萄畑の緑で濃淡の翳りをつくりながら、透明な光の粒子に満ちた空の下、茶褐色の霞の野に遠く広がっていた。ヴェネチアはこの霞の更なる向こうにあるのだろう。窓辺の淡い緑のカーテンに波だった。ラグーナの潮の香が風に融けて、あの忘れて久しい官能の香りを運んでいたのだ。
・・・・・・・・・・・・
夕暮れもいつになくゆっくりとしていた。広場も聖堂も運河も紫紅色の暮色の中で千年の息の根を停めたかのように、静まりかえっていた。大鐘楼が広場に影を落いとし,バラ色のドゥカ―レ宮殿は薄紫の大理石に変わろうとしていた。相変わらず影はなく、運河に行き交うゴンドラもなかった。謝肉祭の最後の日だというのに、聖マルコ寺院の扉は閉まったままなのだ。
かって大祭礼の日を、こんな具合に迎えたヴェネチアがあったのだろうか?千年を越えてビザンチンの栄光と繁栄をアドリア海の空と海に欲しい儘にしてきた不倒のヴェネチアだ。饗宴につぐ饗宴にひと時の休息や空白を渇望したとしても少しも不思議はない。しかも選りすぐって謝肉祭の最後の今日という日に・・、僕の想いは、渚に沿ったスキアヴォー二通りから対岸の聖ジョルジョ島に目を移すことでとりとめもなかった。
そうだとも、こうした静謐の日を用意することこそがイエス・キリストの復活に最も相応しいのだ。それをためらわず大胆に実現してみせるのはヴェネチアを措いてあろうはずはがない。聖マルコの遺骸と称して豚の生肉に隠し、825年エジプトのアレキサンドリアから此のヴェネチアに運んできたのも彼らであるのならば、それをネタにヴェネチアを巡礼のメッカにしたてあげ、おおいに利に与かって来たのも又、ヴェネチアではなかったのか。
僕は、この世を劇の舞台と見抜き、仮面を与え、虚実織り交ぜながら人生の劇を大胆不敵に演じ抜いてきたヴェネチア人に、今、限りない共感を覚えるのだ
G・C氏が今宵、素顔を仮面で覆って現われるというのも彼に本意のヴェネチア人が潜んでいるからのことで、それは僕への心からなる歓迎の徴であるに違いない。なんという今宵の静謐。それはこれから始まるであろう予感をはらんだドラマ『劇』の幕前の静寂に見事に呼応しているではないか。それにしても何という静謐!静寂!
カナル・グランデもサン・マルコ広場もラグーナを越えてリドに向こう側のアドリア海に広がる全ての水域、寺院も鐘楼も宮殿も、運河に沿った館もヴェネチアの全ての建物が夕映えに鈍く黄金の輝きをおびて輝いていた。空も又、西から東にかけて次第に朱を帯びながら黄金の光芒を放っていた。そこには金色に輝く荘厳の相を顕在化したヴェネチアがあった。あだかもサン・マルコ寺院の内陣の闇の中で数世紀を息ずいてきた豪華絢爛の黄金のモザイクが、今日という日のこの時刻のために門外不出の扉を開いて繰る出し、ヴェネチアを荘厳の異界の都に変えてしまったのだと思わせた。それにしてもサン・マルコ寺院の入口の扉が閉まったままなのは奇妙なことだが、今になって気が付くのは、実は運河に面した豪華な館だけでなくヴェネチア中の家の扉は勿論のこと、窓ち言う窓が閉まったままであり、その窓すら果たしてあったのだろうかと疑いたくなる様なその完璧さであった。だが僕は、この総てが静止し黄金の輝きを発しながら荘厳に化した世界のなかで唯一つだけゆっくりと移動していく黒い影の形のあるのに気が付いていた。それはカナル・グランデから漕ぎ出してきて今しがたまでサン・ジョルジョ島の島影に包まれるように光芒の帯びに隠れていたが、少しずつ東に向きを取って遠ざかっていく一艘のゴンドラであった。そのゴンドラを独りの影の形が漕いでいた。いや人とゴンドラはおもむろに動いているただ一体の影の形にしかすぎなかった。孤愁漂う黒い影の形はそのまま進めば何処へ向かうのだろうか。リドの島の脇に伸びた石壘のアーチの水門を潜ると外はアドリア海である。なにかに誘われ、駆り立てられてと云うのではなく、さりとて確かな目的を抱いてと云うのでもない。
月や太陽が自明の軌道に沿って地平線に落ちていくように、避けがたい不動の運命に従ってただゆっくりと動いていく。黒い影の形に漂う孤愁は、その運命の糸に操られるのを悟了しながら赴かねばならない諦観の姿に外ならなかった。
大きな溜め息が在った。僕は、その黒い影が人とゴンドラの一体になった形として“見えている”のは、実は、それだけが動いているからであって、若し動き停める時、黒い影は黄金の相に覆われ消滅するように“見えなく”なってしまうのだと直感した。ヴェネチア全体は黄金に輝く不動荘厳の相に静まりかえっていたからである。黄金は、動きを停めようとする影や闇を待ち受け、その全てを吸収し尽していく。その為だろう。人間は古来よりそれに聖なる形象を与え暗黒の暗闇に安置した。ヴェネチアは如何ほどの闇と影を吐き出しまた呑み干してきたのだろうか?サン・マルコ寺院の内陣の暗がりにあって世紀し亙り影と闇を吸収し続けてきた黄金のモザイク。
それが今宵は不出の扉より繰り出してヴェネチアを荘厳の都に変え謝肉祭の最後を飾っているのではないのか!舞台は整っているのである。重層する幾つもの時代を経てヴェネチアが蓄えてきた無量の闇と影が日暮れとともにマンとを翻し仮面を装い黄金の表層の裏面の底知れぬ深みから復活してくる。そしてサン・マルコ広場や二本の柱に守られた此の祝祭のピアッツエッタはひと時、復活した死霊賛歌の華麗な舞踏の渦に席巻されるのだ。今宵の黄金の静寂はヴェネチアの絢爛豪華な舞台のために用意されていたのだった。
静かだった僕の心は祝祭の劇の前触れに次第に期待と興奮の度合いを昂かめていた。楽しみに待っていよう、いま暫く。未知なるG・Cが現われるのも間近である。それまでに今一度『動いて行く黒い影』を追っていくことにしよう。
ゴンドラの影の形は小さくなってリドの水門に近ずいていた。彼方にアドリア海が拡がり空と海の接する東の最果てに燃えるような金色の厚い帯が空と海の両方から湧き出て南北に伸びている。「黒い影」は明らかにその帯に向かって進んでいた。影は次第に小さくなって点となり動かなくなり最後に金色の帯に融けて見えなくなってしまうだろう。僕にはそれが「影」に約束された動かし難い運命であるのが判った。「影の形」は一旦は黄金の中で形を消滅しそこに留まるだろう。如何ほど留まるかは知る由もない。確かなのは今宵のヴェネチアの謝肉祭の様な日に黒衣を装い黄金の仮面を付けて祝祭の舞台に現われて来るだろうということであった。
影も闇も不明なものの全てを覆い隠し呑み尽す黄金の恐るべき力、それが絶対の消滅でないことを祝祭の舞台に架けて黙示するヴェネチア。存在の「実」も「影」も、「生」も「死」も、
けだし此の世に現れ命を息する機会を与えられた人間の無にも等しい微々たる力が、そうとしか区別し名ずけようが無かったための貧しい名称ではなかったのか、と僕には思えてくる。そして今日という日、僕はこのヴェネチアに在ることに譬えようもない戦慄に等しい喜びを覚えずにはいられない。なおのこと見知らぬ友、G・C の深く巡らした驚嘆の演出に言い知れぬ友情を感じない訳にはいかない。所で親愛なるG・Cよ、そろそろ僕に現れて来てほしい。
・・・・・・・・・
渚さに一陣の風が立ち、金色のさざ波が瑠璃色の波紋を起こした。一艘のゴンドラが目の前の船着き場に近ずいていた。僕が「影の形」の行き先に気を奪われていたからであろう。金色の残照を浴びて逆光のなかに全体の輪郭を失った影絵の様で、さざ波に大きな波紋を描きながらラグーナの水底から浮き出てきたとも思われた。見知らぬ友G・Cが現われたのだと、戦慄が足元から背中に走って言い知れず心が震えた。僕はやはりある種の不安を抱いて此の瞬間を待ちつずけていたのである。第一G・C のイニシャルをもった友が今までに居たのかどうか、何かの機会に或いはいきずりに親しくなってお互いに名乗りあい、記憶からは完全に消えてしまった見知らぬ人であるのか、それすら定かでない。だのに僕はわざわざ旅先のシエナから一日をかけてヴェネチアへ来たのだ。何のことはない。それがいつもの僕の流儀であり、風向きに合わせて運命が操る凧糸に繋がっていると言うだけのことだ。何もエトルリアの鳥占いを煩わせる事もない。見知らぬ男が残した流麗な文字とG・C のイニシャルは僕にとっては運命が与えた一個のダイスであり僕はそれを未来の地図の上に投げたにすぎない。僕にとって生涯を予め定められたあの「安定した」、「確実」な生き方、その為に世間からは信頼され、うまく行けば尊敬もかち得るだろうということなぞ、六面が全て「吉」の文字で刻まれたインチキなダイスにしか過ぎず、塵箱の隅に蹲くまった退屈な世話話でしかなかった。シエナを訪れていたのもドゥッチョウの「マエスタ」の荘厳性を構図の神学的図像学的解析で証明してみようという殊勝な心掛けからではなく、シモーネ・マルティ―ニやドゥッチョウがあの茶褐色の静かで小高い丘上の街で春の日を楽しんだ様に、「今」の時を超えて「今」の時を友に楽しみたかったまでのことなのだ。「優美で、厳かな楽しみの高み」をモンタルチーノの芳醇な赤ワインで心いくまで味わいたかったのだ。
そして「今」は、ヴェネチア。僕はジョルジョーネが幾つかの深い経験から得た劇的イリュージョンを統合して描いた、あの「テンぺスタ=“嵐”」の画像にも匹敵する場面を目の前にしながら、同時にその中に僕がいる。それを舞台に圧縮された人生の劇が今まさに始まろうとしている。・・・ゴンドラは船着場の渚に着いた。
―――――――――――――
ジョヴァンナ・カヴァッリ:黄金の仮面を架けて緋色の衣裳を漆黒のマントで覆い現われる。
Bar Florian;コーヒーの香り立つ。
「ジジ、お待たせしましたわ、私、誰だかおわかりになって?」
「え?・・・その声は・・、まさかジョヴァンナ、・・・ジョヴァンナ・ヴェッツア― ニ?」
「まあ嬉しいわ、ジョヴァンナよ、私の声お忘れでなかったのね、でも今はジョヴァンナ・カヴァッリ」
「はっ?・・・Giovanna Cavalli!・・・、するとシエナで僕にメッセージをよこしたのは・・G.C つまり君というわけ? まさか、可愛い少女は僕のことを“素敵なおじさん”とか言っていた。それにあの筆跡はまぎれもなく男のものだ。」
「おほほ、ジジ、貴方早とちりだわ、私、メッセージの主人公ではありませんわ。第一、シエナになんか行ってませんもの、
若しそうだとしたら私、遠くからでもきっとじじ!と叫んで飛んで行ったわ。でも無理ないわ・・・おなじイニシャルですもの。実はその方、遠い私の御友達なの、「遠い友達?・・男の・・」
「そう、そうなの、申し訳ないわ、その方の代わりに私、此処へ来たの。わけは聞かないで、ただあの方、急に旅立たねばならなかったの・・
「おかしな話だな。そしてG.C と言う方のフルネームとは?」
「今は申し上げられませんわ、言えることと言えば、ジジとナポリでお会いするずっ以前からの古い時を越えたお友達なの、
私、以前に古いヴェネチアに絡んでその事を貴方に語った覚えがあるわ、・・・私には、時を越えて消えることのない「影」の男がいると、じじ、その時貴方はおっしゃったわ、『そんなあてもない「影の男」とは別れろ』と、妬いていたわね、その男よ!・・ヴェネチアに生きる影なの、・・
G.C!、世紀を越えてこれと思う女を見詰め離すことのない影の男・・・」。
「じゃ、ジョルジョ・カヴァッリとでも呼ぶ男かな?」、いいえ違うわ「カヴァッリというのは、ジジとあの夏、ナポリのヴォーメロの丘でお別れして間もなく結婚した男の姓よ。画家だったわ・・ジジと同じように、私がヴェネチアの女というだけで夢中になったのよ・・変わ ってるわね」・・・さて、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」 抒庵
Ⅱ.
東雲の
佐保の山辺に
白衣の
にほうが如く
霞み棚引く
何処かで、瑠朧の春を謡う女人の声がしていた。のどかでまろやかなその声に何故か覚えがあった。何時の頃からだったのだろう、若しかして遠い昔、僕が生まれてくるずっと前から聴いていた様な気もする。
いつの時代にも男たちが抱き求めている若くて美しい“にほうがごとき”女人、それでいてほのかに母性。ふと振り返り、抗い難く抱きしめたくなる様なあの艶麗な女人の声なのだ。
謡いはちかくに聴こえていた。円照寺を登る山の辺の曲がり路でその声は現われた。若草の萌える様な緑が、どこかで見たことのあるその顔に映えて眩ゆく思はれた。「あら、やっぱりいらして下さったわ、お待ちしてましたの」、謡いを停めたその声は明るく弾んでいた。「あ、貴女は・・・」僕は思わず息を呑んで小さく叫んだ。春霞の中に妖しく木蓮の蕾が白く花開いたと思ったからだ。
「さ、何もおっしゃらないで・・・」、女人はふと寂しげに微笑むと僕から言葉を消してしまった。久しい出会いに僕は、嬉しくもどこか物悲しい気持ちを併せ抱きながら肩を並べ山の辺の路を登り始めた。女人はただ幸わせそうだった。心に通うだろう男と二人でいることが嬉しいらしく、それをひたすら言葉に顕わした。「貴方を最後にお見かけしたのは、確か浄瑠璃寺の池のほとりでしたわ、それも随分昔の事、木津の埋谷に禅竹の墓所を詣でに行くとか、土地の未だお若い陶芸家の方と御一緒でしたわ。
お二人でとっても楽しくお話しなさっていらしたのを私、興味深くお聴きしておりました。秋の日の午後でした。貴方は私がずっと近くにいるのに、少しもお氣付きになりませんもの。無理もありませんわ、」女人は明るく笑い、その笑いが葉隠れにこぼれた。
僕は記憶の糸を昔にたぐりながら、山あいの木立に覆われたその平安の寺の幾つかの情景を憶い出していた。木津川の両岸に急に山が迫る鹿背に窯を営む男の案内で、初めて訪れた時のことだったろう。秋とはいえ夏を惜しむ気配が、軒下の露地や茜色の雲を映す池の面に在った。人は疎らだった。古寺巡礼の女子学生らしい数人と二組の初老の夫婦の外は思いだせない。若しかしたら居たのかもしれない。僕達に気付かれない様にひっそり居たのかもしれない。何故言葉をかけてくれなかったのだろうか。でもその事が今、
とても嬉しかった。だが若しかしてあの時の・・・?僕はふと池を巡って西方に向かう位置にすわった時のことを思い出そうとしていた。女人は少し悪戯っぽく僕の顔を覗きこみながら、楽しそうに続けた。「あら、探していらっしゃるのね。そう、そうだわ私、あの時貴方の見ておられた視界の中に居ましたのよ。貴方は池を隔てて本堂の閉じたままの白い障子をじっとご覧になっていました。障子の裏側では、九体の阿弥陀仏が並んで座り閉じられたその障子越に池の面をただ黙然と見下ろしていました・・・」、「あっ、もしやして・・・でもまさか、」僕は一瞬呆然として歩みを停めてしまった。そしてその時の光景が白昼夢を見るように蘇ってきた。あれはやはり、本当に起きた事だったのだ!幻想なんかではなく実在したのだ。あのとき僕は池の面を見ながら一念に念じていた。「そうでしたわ、貴方はひたすら極楽来迎を見たいと念じておられました。白障子が開いて金色の仏が現われ、その御姿が水面に映り揺ら揺らと立ち上がるのを熱心にお待ちになりました。私は本堂の軒下の露地に立って一緒に念じておりました。・・・時が経ちました。本堂の裏の森に陽が沈み辺りに夕靄が忍び寄っていました。その時でしたわね。貴方はとうとうご覧になったのです。そして・・・」そして僕は正に障子が開かれ金色来迎の場面を映す池の水面に、九品の仏と共に、幽艶な姿を現した一人の女人いたのを判っきりと思いだした。「あっ、あのときの女人は・・」僕の心を悲鳴に近い喜悦が走った。それは池を挟んで本堂と僕を結ぶ視界の間にある池の縁の石灯籠の傍らで起きたことだった。いやその灯朧籠自体が女人に変化したのだとばかり思っていた。
「ほら私、いましたでしょう、お判りになって?・・私、御仏と共に貴方に現れましたわ。貴方の御熱心な念願を叶えてあげたくて、そして貴方にお会いいたしたくて・・」、女人の声はどこまでも晴れやかで優しく、僕の昂ぶった心を鎮めていった。のどかな春霞が山の辺の起伏を包みこみ、言葉にならない悦びが女人の上気した横顔から伝わってきた。
あてもなく山の辺の路を辿っているうちに、とある小さな古池にでた。池の面が、低く垂れ重なりあってゆっくりと過ぎて行く雲を映していた。近くに咲く木蓮の白い豊麗な花弁が、女人の精であるかのように思われた。明るいなかに憂愁の翳りを忍ばせて女人は微笑んだ。「いつの頃でしたかしら、大和路の名も無いお寺でしたわね。雨に濡れながら散って行く山門の八重桜の樹の下で、さる方におっしゃたこ事、今も覚えておられる?貴方はその方の命がそんなに長くないのを御存じで、その日を共に過ごされていました・・・、
―花びらが幾つも幾つも散って行く、濡れた地面を赤く染めて行く、まるで無くなっていく命の血みたい―、すると貴方は、“そうかも知れません。でも新しい命の樹を育てるために、だから美しく散るのでしょう。あの枝と別れて地上に落ちる迄の、ため息に似た時間。僕達の命も丁度あの一輪の花ビラの命。いつの頃からか僕は、桜に寄せるこの国の古からの気持ちを受け容れられるようになりました”。その貴方の言葉を聞いて女の方は心持ち微笑んでいましたわ。・・・今も同じお気持ちをもっていらして?」、女人は少し揶らかう様に尋ねた。僕はしばらく間をおいて答えた。「今の今、過ぎて行く瞬間以外にあてになるものがあるとは思えない。その瞬間だって本当は在るか無いかの様なもの、在ると言えば在る、無いと言えば無い。ただ、今こうして生きているので在るというしかない。ですから今日の此の過ぎ行く日を貴女と居ることが、僕にはどんなに嬉しいことか。・・・悦びに満ちた瞬間が限りなく膨らんでいくのですから、だからどの瞬間だっていい、今日の日に散るのならあの桜の花びらになれるのではと・・・」
今にも雨が降りそうな気配がしていた。時折、池にさざ波がたって水面に映った雲を乱した。女人は池の面を見ながら放心の面持ちで聞きいっていた。僕は続けた。「瞬間はそんな時、無限そのものなのかも知れません。此の世の今見えている世界とは別に、不思議な時の流れの世界が在るのを垣間みせている様に思えるのです。それは遠い昔に忘れてしまってうて、若しかしたら此の世をはさんで過去と未来が全く同一である様な、そこへ帰れば、
“ああ、そうだったのだ”と言うだろう世界・・・そうですとも・・・ですから・・・」、「ですから、ふと今の瞬間散れるものなら散りたい、とおっしゃりたいのでしょう・・そうしたら此の世とは別の世界へ私と共に行けるのではと・・・」、女人は放心した面持ちのまま僕の顔を覗き込むと、夢見るように語り続けた。「名残り惜しみて散る花のあるらん。いつの日ぞ相いまみえんと願えど、念ずる心此の世になかりせば、能たわず・・・おわかりかしら、瑠朧の春にこうして貴方とお会いしている私の悦び、どんなにか貴方に感謝して、・・その昔、私、貴方と香わしい春の大和路を歩きたいとばかりに夢見るよう生きておりましたわ。だのに貴方への想いをひと言だに託し得ず、旅立たねばなりませんでした。貴方も又、長い歳月を外国に、・・でも決してお忘れになりませんでした。・・・今散りては叶うまじ、吾が希い汝れに託くせば・・・どんなにか嬉しく、今日こうして貴方と共に居ることのできる此の世の喜び・・・それに貴方には大切なお仕事がおありでしょう・・でも、とても叶わぬお仕事のよう。私、これからすこしお手伝いさせていただきますわ、きっとお役にたてて・・・、わたし、本当は“遠い昔に忘れてしまった”と、先程貴方がおっしゃっていたその世界を熱心に探している方のお傍に居たいのです・・・」。
いつのまにか雲も薄れ、女人の頬にうららな春の陽がさして真珠の輝きを帯びていた。その真珠の輝きこそ女人の想いの底から浮かび上がってくる眩い程の情念に違いない。どれ程の歳月が深い涙の海を輝く真珠に変えてのだろうか。僕の心は、説明し難い深い喜びと底知れぬ悔恨の間で揺れていた。「それは、運命なのだろうか」僕は自問するように尋ねた。女人は黙って答えなかった。こうして無言のまま時が流れた。
陽はようやく遠くの二上山の方へ傾いていた。先程から木蓮の樹の傍らに佇み、落陽を惜しむかの様に西を望んでいる女人の口許に、夢見る様に謡う声が洩れていた。その誦詠の韻は嫋嫋としてどこまでも心を浸していった。
現身(うつせみ)の姿を假りて
夢に舞う
幻の命の美しく
お前に あの方の面俤を
差し上げよう
――――――――
奈良、興福寺に般若の芝と呼ばれる寂れた場所がある。その昔、南大門が在った処に、今は礎石だけが残っている。猿沢の池を見下ろし、かって殷賑を極めたろう。見上げれば五重塔が虚空に宇界を広げる。
或る年の冬、僕は一人で此処へやって来た。雲の低くたれる寒い冬の日だった。風が鳴っていた。梢にも軒下にも、落葉の木立の庭に一匹の雌鹿がたむろしていた。少しずつ目を移すと二面を囲む黄土色の土塀の瓦屋根が竜の背の様にくねっている。傾いた土塀を等間隔にくぎる木の柱がどれもこれも朽ちかけていて、この空間に誰か忽然と現われてくるような気配が漂う。ドキリとして足を停める。土塀の脇か軒下か、それとも木立ちの辺りか雑草の陰か。確かに誰かがいて不意の闖入者を窺っている、・・・居ない。
たれだろう。ここに昔から棲みついている霊なのか・・・、鳩が二羽、目の前に舞い降りてきた。風が急にやんで梢の枝葉の間で灰色の空が低く甘く悲しい。また風がたつ、葉が鳴る。・・・その時だった。何処からともなく韻を含む嫋嫋の音がきこえてくる。松風揺れては消える女人の声か、耳を澄ますとまぎれもなく謡っている女人の声に違いない。縹渺として絶え絶えに風の中に消えていく。
現身の姿・・・
夢に舞う
幻の・・・美しく
・・・あの方の面影を
差し上げよう
あの方に・・・・影を
・・差しあげよう
抒庵
Ⅰ.
旅立とうとしていた。消え去った或る男の足跡を辿ることになるのだろうか。今となっては、男はオリーヴの枝波に漂う微風の影となってしまったに違いない。
「影」が扉を叩いていた。見知らぬ旅への扉を叩いていた。一陣の風が吹き抜けると、芳ばしい香がたった。旅人は歓びに震え、自分の中に蘇生していく何かを、それどころか生まれ変わった自分の分身の現われるのを感じていた。
心のスクリーンに一つの幻像が浮かびそれはあの男の「影」であって傍らに立っているように思われた。「影」は懐かしそうに彼を眺めている様に思われた。やがて その「影」は透明な光を湛えた若者の「像」であるのでは、気付きはじめた。「像」何も言わずただ静かに、微笑を浮かべ佇んでいた。その「影」は未知なる世界、多分、肉体を取り去った無量の時間の中に「影」の男が生き続け、地上からは姿を消したあの国へ彼を連れて行ってくれるに違いない。
「影」は彼の手をとり、彼は「影」に全てを委ねた。こうして旅人も又、かって住んだこともない時間のなかに生きる運命を辿ることになるだろう。彼は迷うことなくそれに従った。全く様相を異にした時間に住まう「影」の「像」と、旅人がどの様に繋がっていくのか、彼には考えてみるのも無駄であり無意味なことに思われた。
旅人は然し、未知なる旅へのどんな前触れも、彼岸に対して抱く胸騒ぎや予でしかないのだ、と感じていた。
抒庵
風閃山門 かぜさんもんにひらめき
星霜去来 せいそうきょらいす
生死無窮 せいしきわまりなく
不知寂滅 じゃくめつをしらず
播州真言宗 若王山 無動寺にて詠む
抒庵
紫に震え コスモスの花びら
純白の小筐に 一輪の
空 崇く透け
野に乱れ咲け
彼岸花
赤き血の
墓の僕(しもべ)
使徒ヨハネ眠れば
抒庵
お前に潜む 果てし無い沈黙
沈黙を宿し 沈黙に抱かれ
お前は 限りなく小さく
滅することもなく 無窮のしじまに漂う
沈黙より生れ 沈黙を宿し
お前は 沈黙に抱かれ 沈黙に帰る
不可知なる沈黙 果てし無く
よも 滅っすることもなく・・・
抒庵
花くるす
花クルス
花クルス
丘の上
蝉まどろむ
紫の影深く
蔦の葉まつらう
群青の空
いにしえに逆らうことなく
黄金の雲 はや
茜色をやどしたり
クルスの傍ら
人影たたずむ
三つの溜め息
詞(こと)の葉をのみ
永劫の時を拍つ
潮の香 西に立ち昇り
白き水鳥は
黄金の雲に立ち向かう
花クルス
花クルス
今日も又
聴かざるや潮の音を
見ざるや海の顔を
抒庵
浜クルス
浜クルス
浜クルス
潮騒の浜に
たゆたう
黒き影は
白州を貫き
深紅の波は
浜辺をあらう
幼き童達は
無心に貝を攫い(さらい)
夕餉の煙
入江に流る
根獅子・・・
何故に安らに暮れゆく
今日もまた
深紅の波は
海と空を洗い
無窮の頂きに
黄金の星を鏤(ちりばめ)る
浜クルス
浜クルス
聴かざる潮の音を
見ざるや童達のたわむれを
抒庵
島クルス
島クルス
島クルス
静かなる
海の上に安らう
いにしえより
殉教の島々の
真中に在りて
穢れなき
処女マリアの
心を宿す
隠れ道
蟹たわむれ
巡る路
女郎蜘蛛
陰を待つ
漁火(いさりび)は
島影に満ち
殉教の魂
夜潮にたゆたう
朝もやの祈り
幼な児ら
ひざまずき
クルスに向かう
背を屈めし老女の和唱
白きヴェールに流れ
七色の光彩
御堂に満つ
島クルス
島クルス
聞かざるや
きょうも又
島に満ちたる
クルスの唱を
見ざるや
夜空に映す
クルスの影を
抒庵
人間が人間であろうと歩み始めた始原の日、人間は微笑みながら地上に立ち、その一歩を踏み出しながら、目の前に広がる茫漠の世界に視線を注いでいた。それが人間であろうとする第一歩であった。古代ギリシャの大地に微笑みながら立ち上がる人間(ペルソナ)、世界を美しいと見るよう預託された人間(ペルソナ)。
最早、それ以外の何かであることはない。こうした人間(ペルソナ)=自分で在り続けようとしてきた不思議を映し視る彼が残った。
気が付くとそれだけが唯ひとつ、ひと時の彼の生命(いのち)の流れに黙ってついてきた言葉があった。言葉は、時の流れに映る彼の姿影の奥にいつも在った。『神(ディーオ)』
抒庵
お前はあの方の夢鏡。あの方はそのお前に映ったご自身の姿を美しいと見確かめられ悦ばれるいない。お前は、生命(いのち)のお前に宿る此の世の季節にその像(すがた)を結ぶよう黙約されている。あの方の鏡であるお前に映った世界を見られ悦ばれるのを想い、お前も悦ぶがい・・・・・・・。
抒庵
ことばは沈黙に
光は闇に
命は闇の中にこそあるものなれ
飛翔するタカの
虚空にこそ輝ける如くに
『エアの創造』より・・・
Ⅰ.まだ目覚めていたのではない。あの方は微睡み(まどろみ)ながら美しい非の打ちどころのない夢を観ておられた。それはあの方自身そうであるべき姿の夢、“蓮の華”であった。微睡みから醒めながらあの方は、その華の姿を映してみたいと思われた。映し出してみる鏡を創りたいと思われた。美しいと感じる心と歪みなく考える力が与えられた。人間の心と脳裏のスクリーンに華はその像(すがた)を映し始めた。又、人間は自分があの方によって創られつつあるあの方の鏡であることを少しずつ気付きはじめた。そして、その鏡が結ぶ像の姿をあれこれコピーしようと試みた。でもあの方は、未だかってどれを正確な姿ともおっしゃらない。あの方は沈黙し黙示なさるだけである。
Ⅱ.美しいと感じる後背にあの方の存在を感じないだろうか。夜空を見上げて又、蓮の華を観て美しいと魅せられる魂にはあの方のナルシスムが影のように寄り添ってはいないだろうか。あの方は人間の魂を透して自ずからの夢に結ばれた世界を美しいと感じたいのであろう。魅せられたいのである。人間がそうであるように働きかけておられるようだ。
人間は、自分自身を代行するものとして作り出したコンピューターが勝手に作り主の人間から能力を奪って離れていくように、あの方か勝手に離れようとしている。何故だろうか。
抒庵
スペインの真昼、光の中に闇を視た男、幻覚だろうか、そこに現れる幻像をゴヤは描いていた。乾板に焼き付いたネガティーブの現実を投写した。人間についての、社会についての失意、虚妄の栄光に決別して闇を視る人へ、「巨人」と「我が児を喰らうサトゥルヌス」、巨人にもサトゥルヌスにもゴヤ自身が投影されている。だがそれよりも、「創造主は自ら創った人間の悲惨を嘆き、その愚かな姿に遂には狂人と化し・・・喰べてしまった」。この単純なイメージに創造主と人間の関係を暗喩したのかも知れない。神はよかれと思って【人間】を創られたであろうに。人間の救いようもない愚行は神を狂わせてしまった。
この二点の作を観ていると僕には、スペインの荒野に展に向かって拳を上げ一人慟哭する人間ゴヤを見る想いにとらわれる。
抒庵
(A BRIEF HISTORY OF TIME)を読んでいる。
面白い。僕は思いつくまま余白に感想など書き添えた。
Ⅰ.人間の頭脳は本来、宇宙構造のコピーであろうとしている。そこには両者がアイデンティティを確立しようと試みる何かの意志が働きかけている。・・・
Ⅱ.地球が宇宙の中心である。と、そう考えたのは人間の過信と未熟な知識から生じたのだろうか?確かにそうかもしれぬ。が、創造主の隠された巧まざる意図があるのでは・・・創造主は先ず人間が宇宙を前にして自身をもつよう意図された。
Ⅲ.第一原因・・・零とか無、非存在の存在とか、言葉にしたら奇妙な語呂、言葉にならないイメージ、言葉の掌からすり抜けていくイメージ、・・・だから人間は「神」としか言う外ない。
Ⅳ.およそ一万年前に遡る文明の夜明け、百億乃至二百億年が経ってようやく宇宙は、自分自身を映す鏡(人間)を創り出し、それも1万年程前から、らしい像を結び始めた。(人間の頭脳、イメージと言語)
Ⅴ.零点に於ける無限大(密度)、思考の抽象性と物質の境界を超える想像力がくり出す言葉、そして物理的定義不能、不可知。
Ⅵ.所で何故、人間の知性も感性も宇宙の完全な記述を欲するのか?何か忘れてしまったもの、失ったかも知れないものがあると、「心」のどこかで感じているからだろう。そのように感じさせる何かの働きが遠いみちの彼方から(多分、物理的定義不能な零点)からやってきているからだろう。それにその心は美しい存在としてその像(すがた)を夢みようとする。だから美は空の空、形而上の事柄なのだ。
Ⅶ.何千億の星と銀河、赤色偏性宇宙の膨張・・・益々面白い。追えば追う程宇宙は益々逃げて行く。気が付くといくらでも大きくなる。いくらでも、とは窮まる所なく光を追っかけながら光を越えるあてもなくということだ。
Ⅷ.1951年、カソリックとビッグバン理論・・・神の存在を揺るがす物理学理論なんかありあしない。・・・ということだったのかな。
多分、「神は光なり。全てをあまねく照らす光なり。全ては光を越えること能わず」と。
Ⅸ.零と無限大を消す方法、量子効果を考慮に入れると特異点は消えるという。波の粒子。形而下と形而上の間に、物質と精神の間に、言葉と言葉を拒むイメージの間に、時間と永遠の間にトンネルが見つかったというわけだ。それはお目出でたい。そこで並みの粒子がトンネルを通過するというわけだ。古代のギリシャ人は陶土を捻りながら波状文様と人間の間のトンネルを難なく発見した。これをトンネルの原型(アルケタイプ)ということにしよう。彼等は最初の波の粒子の民だった。
Ⅹ。クオークと反クオーク、宇宙と反宇宙、物質と反物質,色(しき)と空(くう)のようでやはり違う。色(しき)の棲(すみか)と空(くう)の棲(すみか)ということか。
Ⅺ.対称性の法則、CAPと人間の姿だが、心臓は左に一つしか無い。脳も左右とでは機能を異にする。
Ⅻ.光と重力と暗黒点、特異点は質量の究まる零点、そして変相点。
ⅩⅢ.仮想粒子と非存在の存在、生命は何処へ行く?
ⅩⅣ.1981年ヴァチカンでのイエスズ会主催の宇宙論会議、神と宇宙と。いろんな会議、シンポジウムが花咲くなかで、この会議はとび抜けて面白そうだ。
ⅩⅤ.「宇宙はただ存在する」と、ホーキングのこの言葉から僕には次のような想いが浮かび上がってくる。・・・―創造主の夢に咲く蓮の華、人間はその華を映し出してみせる鏡であろうと直覚し、創造主の確かな鏡であり続けようとしている。「美しい花、蓮の華」、人間は創造主が自らの夢を映し出すために創られた鏡であるばかりでなく、それに感応同調しようと試みる存在であるのかもしれない。花があまりにも美しいので、創造主は、「もっと美しいはず・・・」とたえず人間の心に囁き続ける。量りしれないナルシズムとエクスタシー、そして美の根底にあるもの。
抒庵