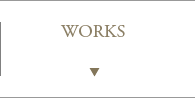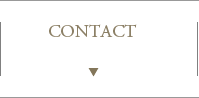Ⅱ.
東雲の
佐保の山辺に
白衣の
にほうが如く
霞み棚引く
何処かで、瑠朧の春を謡う女人の声がしていた。のどかでまろやかなその声に何故か覚えがあった。何時の頃からだったのだろう、若しかして遠い昔、僕が生まれてくるずっと前から聴いていた様な気もする。
いつの時代にも男たちが抱き求めている若くて美しい“にほうがごとき”女人、それでいてほのかに母性。ふと振り返り、抗い難く抱きしめたくなる様なあの艶麗な女人の声なのだ。
謡いはちかくに聴こえていた。円照寺を登る山の辺の曲がり路でその声は現われた。若草の萌える様な緑が、どこかで見たことのあるその顔に映えて眩ゆく思はれた。「あら、やっぱりいらして下さったわ、お待ちしてましたの」、謡いを停めたその声は明るく弾んでいた。「あ、貴女は・・・」僕は思わず息を呑んで小さく叫んだ。春霞の中に妖しく木蓮の蕾が白く花開いたと思ったからだ。
「さ、何もおっしゃらないで・・・」、女人はふと寂しげに微笑むと僕から言葉を消してしまった。久しい出会いに僕は、嬉しくもどこか物悲しい気持ちを併せ抱きながら肩を並べ山の辺の路を登り始めた。女人はただ幸わせそうだった。心に通うだろう男と二人でいることが嬉しいらしく、それをひたすら言葉に顕わした。「貴方を最後にお見かけしたのは、確か浄瑠璃寺の池のほとりでしたわ、それも随分昔の事、木津の埋谷に禅竹の墓所を詣でに行くとか、土地の未だお若い陶芸家の方と御一緒でしたわ。
お二人でとっても楽しくお話しなさっていらしたのを私、興味深くお聴きしておりました。秋の日の午後でした。貴方は私がずっと近くにいるのに、少しもお氣付きになりませんもの。無理もありませんわ、」女人は明るく笑い、その笑いが葉隠れにこぼれた。
僕は記憶の糸を昔にたぐりながら、山あいの木立に覆われたその平安の寺の幾つかの情景を憶い出していた。木津川の両岸に急に山が迫る鹿背に窯を営む男の案内で、初めて訪れた時のことだったろう。秋とはいえ夏を惜しむ気配が、軒下の露地や茜色の雲を映す池の面に在った。人は疎らだった。古寺巡礼の女子学生らしい数人と二組の初老の夫婦の外は思いだせない。若しかしたら居たのかもしれない。僕達に気付かれない様にひっそり居たのかもしれない。何故言葉をかけてくれなかったのだろうか。でもその事が今、
とても嬉しかった。だが若しかしてあの時の・・・?僕はふと池を巡って西方に向かう位置にすわった時のことを思い出そうとしていた。女人は少し悪戯っぽく僕の顔を覗きこみながら、楽しそうに続けた。「あら、探していらっしゃるのね。そう、そうだわ私、あの時貴方の見ておられた視界の中に居ましたのよ。貴方は池を隔てて本堂の閉じたままの白い障子をじっとご覧になっていました。障子の裏側では、九体の阿弥陀仏が並んで座り閉じられたその障子越に池の面をただ黙然と見下ろしていました・・・」、「あっ、もしやして・・・でもまさか、」僕は一瞬呆然として歩みを停めてしまった。そしてその時の光景が白昼夢を見るように蘇ってきた。あれはやはり、本当に起きた事だったのだ!幻想なんかではなく実在したのだ。あのとき僕は池の面を見ながら一念に念じていた。「そうでしたわ、貴方はひたすら極楽来迎を見たいと念じておられました。白障子が開いて金色の仏が現われ、その御姿が水面に映り揺ら揺らと立ち上がるのを熱心にお待ちになりました。私は本堂の軒下の露地に立って一緒に念じておりました。・・・時が経ちました。本堂の裏の森に陽が沈み辺りに夕靄が忍び寄っていました。その時でしたわね。貴方はとうとうご覧になったのです。そして・・・」そして僕は正に障子が開かれ金色来迎の場面を映す池の水面に、九品の仏と共に、幽艶な姿を現した一人の女人いたのを判っきりと思いだした。「あっ、あのときの女人は・・」僕の心を悲鳴に近い喜悦が走った。それは池を挟んで本堂と僕を結ぶ視界の間にある池の縁の石灯籠の傍らで起きたことだった。いやその灯朧籠自体が女人に変化したのだとばかり思っていた。
「ほら私、いましたでしょう、お判りになって?・・私、御仏と共に貴方に現れましたわ。貴方の御熱心な念願を叶えてあげたくて、そして貴方にお会いいたしたくて・・」、女人の声はどこまでも晴れやかで優しく、僕の昂ぶった心を鎮めていった。のどかな春霞が山の辺の起伏を包みこみ、言葉にならない悦びが女人の上気した横顔から伝わってきた。
あてもなく山の辺の路を辿っているうちに、とある小さな古池にでた。池の面が、低く垂れ重なりあってゆっくりと過ぎて行く雲を映していた。近くに咲く木蓮の白い豊麗な花弁が、女人の精であるかのように思われた。明るいなかに憂愁の翳りを忍ばせて女人は微笑んだ。「いつの頃でしたかしら、大和路の名も無いお寺でしたわね。雨に濡れながら散って行く山門の八重桜の樹の下で、さる方におっしゃたこ事、今も覚えておられる?貴方はその方の命がそんなに長くないのを御存じで、その日を共に過ごされていました・・・、
―花びらが幾つも幾つも散って行く、濡れた地面を赤く染めて行く、まるで無くなっていく命の血みたい―、すると貴方は、“そうかも知れません。でも新しい命の樹を育てるために、だから美しく散るのでしょう。あの枝と別れて地上に落ちる迄の、ため息に似た時間。僕達の命も丁度あの一輪の花ビラの命。いつの頃からか僕は、桜に寄せるこの国の古からの気持ちを受け容れられるようになりました”。その貴方の言葉を聞いて女の方は心持ち微笑んでいましたわ。・・・今も同じお気持ちをもっていらして?」、女人は少し揶らかう様に尋ねた。僕はしばらく間をおいて答えた。「今の今、過ぎて行く瞬間以外にあてになるものがあるとは思えない。その瞬間だって本当は在るか無いかの様なもの、在ると言えば在る、無いと言えば無い。ただ、今こうして生きているので在るというしかない。ですから今日の此の過ぎ行く日を貴女と居ることが、僕にはどんなに嬉しいことか。・・・悦びに満ちた瞬間が限りなく膨らんでいくのですから、だからどの瞬間だっていい、今日の日に散るのならあの桜の花びらになれるのではと・・・」
今にも雨が降りそうな気配がしていた。時折、池にさざ波がたって水面に映った雲を乱した。女人は池の面を見ながら放心の面持ちで聞きいっていた。僕は続けた。「瞬間はそんな時、無限そのものなのかも知れません。此の世の今見えている世界とは別に、不思議な時の流れの世界が在るのを垣間みせている様に思えるのです。それは遠い昔に忘れてしまってうて、若しかしたら此の世をはさんで過去と未来が全く同一である様な、そこへ帰れば、
“ああ、そうだったのだ”と言うだろう世界・・・そうですとも・・・ですから・・・」、「ですから、ふと今の瞬間散れるものなら散りたい、とおっしゃりたいのでしょう・・そうしたら此の世とは別の世界へ私と共に行けるのではと・・・」、女人は放心した面持ちのまま僕の顔を覗き込むと、夢見るように語り続けた。「名残り惜しみて散る花のあるらん。いつの日ぞ相いまみえんと願えど、念ずる心此の世になかりせば、能たわず・・・おわかりかしら、瑠朧の春にこうして貴方とお会いしている私の悦び、どんなにか貴方に感謝して、・・その昔、私、貴方と香わしい春の大和路を歩きたいとばかりに夢見るよう生きておりましたわ。だのに貴方への想いをひと言だに託し得ず、旅立たねばなりませんでした。貴方も又、長い歳月を外国に、・・でも決してお忘れになりませんでした。・・・今散りては叶うまじ、吾が希い汝れに託くせば・・・どんなにか嬉しく、今日こうして貴方と共に居ることのできる此の世の喜び・・・それに貴方には大切なお仕事がおありでしょう・・でも、とても叶わぬお仕事のよう。私、これからすこしお手伝いさせていただきますわ、きっとお役にたてて・・・、わたし、本当は“遠い昔に忘れてしまった”と、先程貴方がおっしゃっていたその世界を熱心に探している方のお傍に居たいのです・・・」。
いつのまにか雲も薄れ、女人の頬にうららな春の陽がさして真珠の輝きを帯びていた。その真珠の輝きこそ女人の想いの底から浮かび上がってくる眩い程の情念に違いない。どれ程の歳月が深い涙の海を輝く真珠に変えてのだろうか。僕の心は、説明し難い深い喜びと底知れぬ悔恨の間で揺れていた。「それは、運命なのだろうか」僕は自問するように尋ねた。女人は黙って答えなかった。こうして無言のまま時が流れた。
陽はようやく遠くの二上山の方へ傾いていた。先程から木蓮の樹の傍らに佇み、落陽を惜しむかの様に西を望んでいる女人の口許に、夢見る様に謡う声が洩れていた。その誦詠の韻は嫋嫋としてどこまでも心を浸していった。
現身(うつせみ)の姿を假りて
夢に舞う
幻の命の美しく
お前に あの方の面俤を
差し上げよう
――――――――
奈良、興福寺に般若の芝と呼ばれる寂れた場所がある。その昔、南大門が在った処に、今は礎石だけが残っている。猿沢の池を見下ろし、かって殷賑を極めたろう。見上げれば五重塔が虚空に宇界を広げる。
或る年の冬、僕は一人で此処へやって来た。雲の低くたれる寒い冬の日だった。風が鳴っていた。梢にも軒下にも、落葉の木立の庭に一匹の雌鹿がたむろしていた。少しずつ目を移すと二面を囲む黄土色の土塀の瓦屋根が竜の背の様にくねっている。傾いた土塀を等間隔にくぎる木の柱がどれもこれも朽ちかけていて、この空間に誰か忽然と現われてくるような気配が漂う。ドキリとして足を停める。土塀の脇か軒下か、それとも木立ちの辺りか雑草の陰か。確かに誰かがいて不意の闖入者を窺っている、・・・居ない。
たれだろう。ここに昔から棲みついている霊なのか・・・、鳩が二羽、目の前に舞い降りてきた。風が急にやんで梢の枝葉の間で灰色の空が低く甘く悲しい。また風がたつ、葉が鳴る。・・・その時だった。何処からともなく韻を含む嫋嫋の音がきこえてくる。松風揺れては消える女人の声か、耳を澄ますとまぎれもなく謡っている女人の声に違いない。縹渺として絶え絶えに風の中に消えていく。
現身の姿・・・
夢に舞う
幻の・・・美しく
・・・あの方の面影を
差し上げよう
あの方に・・・・影を
・・差しあげよう
抒庵