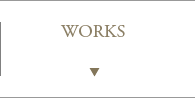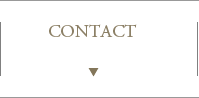Ⅰ.
旅立とうとしていた。消え去った或る男の足跡を辿ることになるのだろうか。今となっては、男はオリーヴの枝波に漂う微風の影となってしまったに違いない。
「影」が扉を叩いていた。見知らぬ旅への扉を叩いていた。一陣の風が吹き抜けると、芳ばしい香がたった。旅人は歓びに震え、自分の中に蘇生していく何かを、それどころか生まれ変わった自分の分身の現われるのを感じていた。
心のスクリーンに一つの幻像が浮かびそれはあの男の「影」であって傍らに立っているように思われた。「影」は懐かしそうに彼を眺めている様に思われた。やがて その「影」は透明な光を湛えた若者の「像」であるのでは、気付きはじめた。「像」何も言わずただ静かに、微笑を浮かべ佇んでいた。その「影」は未知なる世界、多分、肉体を取り去った無量の時間の中に「影」の男が生き続け、地上からは姿を消したあの国へ彼を連れて行ってくれるに違いない。
「影」は彼の手をとり、彼は「影」に全てを委ねた。こうして旅人も又、かって住んだこともない時間のなかに生きる運命を辿ることになるだろう。彼は迷うことなくそれに従った。全く様相を異にした時間に住まう「影」の「像」と、旅人がどの様に繋がっていくのか、彼には考えてみるのも無駄であり無意味なことに思われた。
旅人は然し、未知なる旅へのどんな前触れも、彼岸に対して抱く胸騒ぎや予でしかないのだ、と感じていた。
抒庵