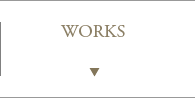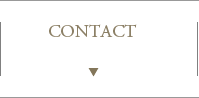「少女たち」や「山」、「花」をモティーフにした作品が、それも近作ほど大層心を打ち素晴らしかった。若い頃のある時期ポール・ゴーガンに魅かれたということだ。画面の表層では判っきりしないが、
彼の内面のかなり深層の部分を浸しているような所がある。僕にはそれがかえってこの近年の作に読みとることが出来る。韻とか音楽に近い何かを表象形象に近ずけようとしている。韻象だろうか。それはゴーガンの場合も同じだ。
僕は想い出していた。高校を卒業してぶらぶらしていた十八歳の頃、久留米の母方の祖父の家の廊下に埃をかぶって積み上げてあった「みずえ」の中に「ゴーガン」特集を発見した日のことを。ともあれあの日ゴーガンによって僕は未知の世界に出発しようと心に決めたのだった。
それは生命の若さを純粋無垢な何ものか、―処女地に駆り立てる果てしないパトスのようなものだった。あの頃、僕の心は既に引き裂かれ、悲しく魂は飢えていたのだ。 抒庵