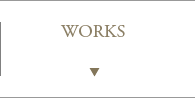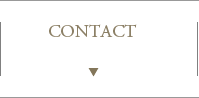私の彫刻との出会いと歩み
私が彫塑との最初の出会いで、ひどく直感したことは、彫刻とは常々不安に曝されている己の精神と肉体の存在を、生命力と精神を内在する形ある量体の存在として覚醒しようと試みる全身的な行為(精神と肉体を一体化した行為)であって、その結果、それは不動の表象形象に結晶していく、ということであった。私は中学を終え23才の頃まで人生を導いてくれる確かなものを探しあぐねておおいに悩んでいた。最初は音楽にそれを求めていたと思う。だが彫塑との出会いによって、その後はこの確信を揺るぎないものとしながら造形を今日まで続けている。
1960年、満29才を近くに迎え、私は祖国を離れイタリアに向かう。以後、1978年に帰国するまでの間、ヨーロッパ各地を訪れ、その間、一時帰国の機会を得て京都に旅する機会があった。そこで出会うこととなった貴重な体験が、私に異なる異質の文化体系の狭間に在る私自身を強く意識させただけでなく、その意識の底流に分裂の畏れを抱きながらも、いずれはこれを克服しながら進まねばなるまいという予感を感じていた。だが如何様にして?・・・そしてその答は?・・・此の事が私の歩みの中で折りにふれ影の様に問いかけてくる言葉であった。
このたびの「観音菩薩像」も又、その答を求めての一里塚であるのかもしれない。今、このことに関連して少し話題を変え、異質の文化との出会い、それによって生じる葛藤、その克服について語ることにしょう。
――――――――――――――――
古代ギリシャ・ローマに始まりルネッサンス期、15,16世紀までの彫刻を、日本の自然・風土に置いて観るとする。また逆に飛鳥から鎌倉時代に至るまでの日本の彫刻をギリシャ、イタリアの自然・風土に置いて観るとすれば、どんな印象を受けることになるのだろうか?・・・先ずは木と石の文化の違い、異質の文化である何かを際立たせることにならうだろうが、それと同時に人類の文化の共通分母として何かが存在することに気付くことにもなるだろう。その認識の度合いは恐らく個々の心のひろがり、洞察の質と深さによって異なってくるだろう。異文化を強く体験してきた作家に生じる謂わば不連続と連続性の感覚体験は、同時に異なる両者の歴史時間を創造の坩堝に投じながら、どの様にしてもう一つの形式、謂わば第三の形式に収斂していけるのだろうか?・・・・これは単に芸術・文化の分野に留まる問題ではなく、地上に生きる人間の全ての営為(思考、行動)に求められている命題ではないのだろうか?・・・
此処で理解を深めるために一人の哲学者と、二人の作家(作曲家と陶工)を紹介しよう。
1980年代の半ば頃であったかと思うが、イタリア文化会館館長デ・マルキス氏時代のさる女性キュウーレイターのお宅で哲学者・今道友信氏と作曲家・武満徹氏を囲んだことがあります。その折、今道氏の語られた一つの詞が大変に印象深かったのを想い出します。それはラテン語の合成による学問名で
「CALONOLOGICA」という言葉です。
CALON 美
ON 存在
LOGICA 理性
の三つのラテン語の合成語で、この三つの言葉は生命(生)と時間を内在しながら「存在」が「美」であり、「美」が「存在」であることを暗喩しつつ形象と音像に結実していく。・・・その夜はこの言葉をめぐって話が弾んだ。・・・ 思うに、武満徹の作曲のプリンシプルはこの言葉に求められ集約されるのではないのだろうか?
――武満徹(1930-1995)は異なる二つの文化の伝統楽器によるオーケストラ編成によって両者を融合する表現する表現様式を提示しながら伝統文化と異文化との激しい接触で生じる文化間の断絶と不連続の超克を試みた。
――又、当代・第15代楽家主人:楽吉左衛門(1949覚入の長男として生まれ、1981年に15代吉左衛門を襲名)は、一時ローマに住まい、その異文化の厳しい体験を経て、どの様に楽焼の伝統を拓いていくのか?・・・現在、彼の作陶はその苦闘のただならない様相を鮮烈に物語っている。荒野の地平に不滅の星を追う狼の様に!・・・私は彼の明日に大いなる期待を抱いている。
(*楽美術館2006・Ⅸ・11日発行:「光悦と楽導入・二つの楽茶碗 二人の交友」に注目してみよう。