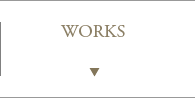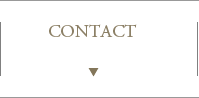ほのかに潮の香が立ち静まり返った部屋にオリーヴの油香が薫った。空気は乾いていて暑く、男は目を閉じたままだった。
コロッセーオ(円形劇場)より左程遠くない古びた石造りのアパートの部屋に女は独りで住んでいた。日除け扉(ブラインド)は閉められていて薄暗く、だが真夏のローマの太陽は白く射るように午後の暑気を日除け扉の隙間から容赦なく送り込んでいた。
簡素な調度品が部屋の片隅を占めるだけの壁を背に、木造りのベッドと小さな椅子があって薄暗い闇の部分をつくっていた。ベッドの脚下の大理石の床には青い布地が敷かれ、男はそこに横たわっていた。影のように、白く揺れる女の背に接して横たわり腰から下はおぼろに闇の中に消えていた。男は目を閉じたまま、女の優しみのあるなだらかな肩の辺りから次第に柔らかい横腹の窪みにそって、又険しく盛り上がっていく張りのある腰の頂きの方へ、右の掌でゆっくりとなぞっていた。弓なりに横臥する女の背をくりかえし確かめるようになぞっていた。掌らは、それが男の行為のなかでもっとも意味のあるものの様に動いていて、その微妙な動きに合わせるように緩やかに沈み、沈んでは昂(たかま)り、又沈みながら長く尾を曳く気息の谷間で油香は立っていた。気息はひととき重なり合ったまま続いたが、やがて離れ離れになり又一つに結ばれた。あたかも舟の艫(とも)にくり出す網のように、泡立つ愉悦と思念の組紐(くみひも)を掌らの艫に曳きながら忘我の海を指していた。
この様にして時は経った。嵐の前触れかのようにそれまで静かだった海の潮の香が少しずつ濃く増していた。男の掌(てのひら)は休みなく滑り、指先に伝わる女の感触を丹念に掬い上げながら大きく迫(せ)り上がり、又沈んでいく。そして窪みや丘が熱気を帯び、湿気を孕み気忙しく形を変え底の芯の方から海鳴りの響きにも似て震えが伝わってくるのを秘かに感じとっていた。震えはしばらく経って嗚咽に変わり息を殺し女は低く呻いた。男は息をのみ気を詰め、そして支え続けた。その苦渋の貌は悲願の成就を祈念する行者のようであり、確かに男は、掌らの中で微妙に変化をしながら絶え間なく形を変えている谷間や隆起や頂きが次第に統合され整った一つの完結した形となって、やがて閉じられた目蓋の裏に美しく描き出されてくるのをひたすらに念じ続けていた。
然し、それは徐々に昂り突如として迫り眩らめく稲妻となって襲いかかってくるあの暴力にも似た悦楽の嵐の中を揺るぎなく通り抜けるに等しく、押し寄せる力に拮抗し堪え忍びながら時を停めることでもあった。時はややもすれば独りでに走り出し暴走しようと機をうかがい待ちうけている。その不意の時は巧妙な思惟の配慮で宥められねばならない。内なる放埓ともいえる強い自然の力に抗い(あらがい)背き(そむき)耐えながら男は、その量感のある未だまとまりのない生きものを支配し統御し、男が抱く一筋の思念の希求してやまない形象に向かって明晰な程に追い上げる外なかったのだ。こうしてやがて訪れて来るであろう形象の美しく豊かに結晶する瞬間をひたすらに念じ待ち続けた。
時が経った。部屋に漂う空気は乾いていて床石は暑かった。その床の上でオリーヴの薫ゆる大理石の裸像はもはや冷ややかな無機質の量体であることを諦め、真奥から表層に向かって火照るように熱くなっていた。波打ち喘ぎ生命あるものに変わろうとしていた。突如として一条の炎が立った。炎は息詰まる瞬間を失神の闇に変えるその中でさく裂し激しく燃え上がった。忽ちのうちに白銀の火花を散らしほとばしる湯の本流となって溢れでた。それは抗う(あらがう)すべての力を一瞬のうちに砕き流し去ってしまう聖なる至高の暴力に違いなく、すさまじい勢いで男を圧倒していった。男の全てを貫き突き上げていく断末魔のけいれんが熱い涙の奔流となって閉じられた目蓋にぶつかり溢れ出しとめどなく頬を濡らし流れ落ちていった。こうして閉じられていた男の目は遂に開き、此の世に初めて視覚を得た人の様に目の前に暁の燭光が射してくるのを見守っていた。ついでその視覚が最初に捉えたものは床に横たわる女の裸像であり、男は盲目の闇の目蓋の裏壁に根気よく彫り続けてきた彫像を今や現実のものとして眺めようとしていた。だが現実は今の瞬間、男を極度に支配した恍惚と陶酔が急速に退潮に転じる流れの中で放心と驚きが加わり、もう一つの恍惚に向かって流れを遡ることであった。
男は遠くから彫像を眺めるよう目の前の裸像を視た。たわわな黒緑の髪が幾筋にも分かれ大理石の背の肌に濡れながらまとわり付いていた。その間から瑪瑙色の女の横顔が透きとるようにほの暗い中から浮かび上がってきた。女の右腕は後ろ手に回り男の首のあたりを先程から触れたままの形で硬直していた。男は修験者さながら幾つもの危うい峠を越え谷を渡り掌の闇の視覚が追い求めていた形を、それに従い根気よく彫り続けていた硬い鑿(のみ)が創り上げたと思われる大理石の彫像の、今初めて熱く濡れて生命の息吹に喘ぐ姿に化身したのを悟った。奇跡に出逢うことが出来たのだという胸をひたす熱い想いが男の中に起き美しく輝くような悦びで全身を満たしていった。痛い程の感動だった。だがその時、目の前を黒く鈍く光りを帯びて走り抜けていくものがあった。男は一瞬ギクリとしたが、それがいつもは何処か幽暗の淵に潜んでいて男を窺い、こうした折にふと現れ、怯えさせてくる実体のさだかでない何物かであることを知っていた。感動と陶酔と恍惚との後に訪れて来る悦びに代わる寂寞と悲哀の前触れであることを、いずれはで諦観しそれを受け容れる外、逃れる術(すべ)のないことも。唯(ただ)、それが訪れて来るまでの束の間、もう一度はっきりと総てを視、確かめておきたいと思った。
薄暗がりの空間に完成したばかりの一体の裸像があった。生命ある形があった。それは人間にとって結極は不可知であることをやめない大自然というものの内に在って、しかもその不測の仕組みが与える苦痛にも似た歓喜の最後の一滴までを背くことなく、人が己の中の自然のおもむくままに受け止め飲み干すことによって、ようやく完成に達することの出来る生命の形であろう。それは大空であり大地であり大海である自然の恵みと破壊の無限の力の摂理から創られる貴い美の形象であり生命の奇蹟とでも云う外ないのだ。過ぎ逝く生命の時の流れに奇蹟のように現れる美の形象という外ない。それは瞬時の間、輝き光芒を残して去って行く。「美しい生命、その形、それを僕は視たのだ!」悲哀と寂寞が既に足下に忍び寄っていた。男は何故か今は素直にそれに寄り添い、そのもののあるがままを愛(いと)おしく受け容れようとしていた。生まれて初めて心からそれに同意を与えようとしていた。残光も影の部分も又、存在の証しであることをひしと訴えているように感じはじめていた。その男の中に今までに経験したこともない転調が起きていたのだ。それは軽い驚きと悦びの波紋を心の片隅にひろげたがすぐに消えていってしまった。