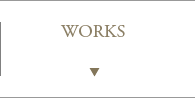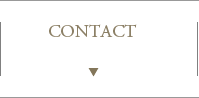イタリアの日々、心に空しく迫り空虚(うつろ)に響くものがあるとすれば、人は生きていることの証しとして遂には美にその拠り処を求めることになるだろう。それすらもなお空しいというのであれば神の前に佇む外ない。 ―美に忍び寄る神の前に―。
美は折にふれ、空しさと神の間の中空にあってしばし光芒を放つ生命あるものの存在の証しであるかの様に現れる。人はそれに出合いそれに溶けあう。時として人はそれに形を与えることによって生き、そこに生の形式を見出すに違いない。
ローマに始まるイタリアの日々は何処に逢着するのであろうか。
そのローマの歴史は、感覚時間の喪失とも思える空間のひろがりの中の存在の空しさを、強迫とも思える生命の充溢、放恣とも思える感覚と官能の豊穣によって、巨大な量体を構築し、絢爛たる装飾を表層に施しながら精力的に埋め尽くし覆い隠そうと企てた業深き人間の歴史ではなかったのか。この存在の空しさに対する観念の強迫、狂暴とも思える現実へのあくなき執着は、ローマをして超現実的様相を帯びさせ、全体を濃密な幻像の舞台に変えていく。それは希(まれ)にみる精力的で享楽的な美の形式であり又、生の形式と思われる。ローマは財を集め技を尽くし,情念の限り精力的に生に執着する。
二千年を超える歴史時間を七つの丘とその周辺に集積したローマは演劇(ドラマ)の舞台であるかの様にそれ自体で人生の劇の舞台となり、美の残照を浴びながら人々はそこでそれぞれの仮面を付け俳優のように人生の劇を演じ情念を生きることになるのだ。だからこそ、いまも量塊であり続け、美の残影を色濃く留めるローマの遺跡は、歴史時間と共に存在に迫る空しさを二倍にも増して投げ返してくる。人は現在(いま)もそこに生まれ住まい、自らの情念に従って、ひと時人生の劇を演じ生きそして去って逝く。旅人も又そこに流れ住まい、人生の情念の劇であることを確かめ去って行く。そこには凝縮した濃密な人間の美的で官能的な生の体験があり現今(いま)に凝縮した歴史時間の体験がある。虚実織り混ぜて重層する生の体験でありながら誰も虚実の間にはっきりとした境界を見ることはない。
ローマの光と影、闇と昼は際立って鋭く深く、ひとつひとつの存在につきまとう虚実の仮面(マスク)のように両者は表裏離れることもなく、ひたすらに存在自体を際立たせる。だが然し人は何を虚、何を実と定めることが出来ようか。ローマの美の実態も虚構も歴史の現在(いま)を生きる者にとって、分かち難い唯一の存在であり続けるからに外ならない。悩める魂を鎮めようというのであれば十字架の光と伽藍の中に佇むがよい。
恐らく、それ自体で感覚的で官能的な知性があるように、それ自体で知的であり続ける感覚や官能があるだろう。それは生きていることへの問いかけを機縁とし、又それからの答えを機縁として豊穣なる生の形式を獲得し展開していくと思われる。だがそれは魂の試練であることに変わりはない。悦楽と苦渋を表裏として・・・。
ローマの舞台を去って想うことは多い。その瞬間々々を惜しみなく生き美的に演じたというのであれば、経験を更なる生の形式に止揚し昇華しようと試みたのであれば、いみじくも或る一つの美の形式を想うに至ったであろう。ともあれあの時、オリーヴの樹海を透し、何故であろう。モン・レアーレ大聖堂の回廊{キオストロ}に佇む時、オリーヴの樹海のたわわに波打つ想念のなかに、ギリシャと覚しき風韻の美しく流れていたのは・・・。
抒庵