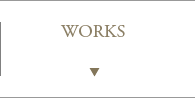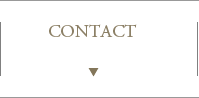1985年4月6日、京都国立博物館「大徳寺名宝展」にて、室町時代の伝蛇足筆になる真珠庵の障壁画・四装花鳥図の最左端に目を奪われる。
竹篠の葦踏みより頭を少しもたげ右手に歩み出ようとする気配の白鳥の表出描法に於いてである。一切の輪郭線を許さず唯、竹篠の繁みのみが白鳥の存在を浮揚させている。白鳥の体表には調子を探る暈(ぼかし)も描点も線もない。空白! 真白い白抜きのただそれだけの表出。しかしそこに何ものも存在しないと思われた空間は突如として存在そのものの場と化していく。白鳥は筆跡を留めぬ無為の描法により悠然と現れる。何故であろう? 京博大徳寺名宝展、僕はこの一点に向かって感覚の全てを吸収されてしまっていた。
伝蛇足筆四装障壁画左端に表出された白鳥と、左端より二装目にあって渺々湖面に浮上する月は、蛇足にとって実は先刻そこにあった姿,従って今は既にそこに無く不在になってしまったものの描出であると思われる。今そこに不在のものは先程確かにそこに存在していた。
空間は時間の経過に従い形象によって充足もされ空虚にもなりうる。が、その時その空間を充足していた白鳥と月は不在の今どの様にして描出することが出来るのか。不在になった形象の表出とは何であるのだろうか。
目前の空間が白鳥と月によって充足されていたその時と、その時、月と白鳥によって充足されていたその空間を今どの様にして示唆することが出来るのだろうか。表出することが出来るのだろうか。月も白鳥もそこに不在になってしまった今の時、虚ろとなった空間では点も線も暈しも非在となり存在し得ないのである。従って点、線,暈しによって表出することは不能となっている。であるのなら、不在の今の時となってみれば虚となってしまった空間そのものにこそ解決の鍵が隠されていると思わねばなるまい。虚の空間を絵画空間として位置ずけることに関わるが、それは如何なる意味をもつことになるのだろうか。空虚空間の作画上の美学的意味と方法を問うことである。
視線を移せば白鳥と月以外のもの、草木自然の形象は依然として その時も今も継続して同一空間を占め続けている。その時、画面全体は存在によって充たされていたのである。しかし今や存在と非在が同一画面の空間域で生じることとなった。充溢均衡状態にあった球体の中に真空の隙間が生じたのである。その時、充足の空間と虚の空間の間、存在と非在の間に力関係が起生する。同一画面の正と負の二つ空間の間に生じる或る力関係である。それは表裏する運動を喚起する。存在は非在の空間に侵入し、充たそうと働く。非在の空間は存在の空間を呑み尽くそうとして働く。正確には恐らく虚の空間、空白の空間は「充足の空間」の感覚総体を融解しながら吸収し充溢しようとして働くだろう。充足の部分が空間の部分に侵入し充たし全体が充足の状態に達しようとするのである。非在は存在を成り立たせている感覚を吸収し始める。それは再び画面全体により均衡の状態を取り戻そうとして続くのである。しかし この感覚量の力関係と運動とは主観の介入そのもの以外の何者でもない。否、主観の介入によってしか生ずることが出来ない「美」感覚の整合充足運動であるという他ない。主観の介入によってしか果たすことの出来ない感覚の臨界点が「美」の構造によって設定されているのである。主観はついに目覚めうごかされ感覚の覚醒を喚起する。
蛇足にとって、しかしこの「美」の構造は作為としての設定であったのだろうか。予め計算された仕掛けであったのだろうか。蛇足はひたすら記憶の中に生きる白鳥と月の最も美しい瞬間をずっと視続けていたに相違ない。その美の瞬間を内観に焦刻していたのである。刻印された「時」は蛇足によって内観視界に時を停められてしまった。かくてそこに存在した空間、そこに存在した時は、あたかもそこに今の時点の生起であるかのように蘇ってくるのである。ある強力な磁場の触発する想像力が虚の空間、空白空間に描き出した映像であり、極めて確かな実在感を伴った幻像(イリュージョン)であると言えよう。周囲の感覚自然は継続して変わらずそこに存在し続ける。そして一見何事も起こらなかった様な佇ずまいをとり続ずける。観る者の(=外観は)感覚を吸収し続け実在感を昂めながら月はやがて天空に昇り、白鳥は湖水に向かって足を滑らせる。実はこのような時間の経過は先刻起きてしまったに違いない。画面のそこに設定された空白空間に向かう注視は、それ以外の点、線、暈しによって描出されている世界を裏面へ静かに後退するよう促すと共に、空白空間の中には、その後退しながら融解していく世界の感覚総体が侵入し始める.そこには点も線も暈しも無く、それによって特定の影姿に仕上げようとするそうした手掛かりはひとつとして無い。虚の空間は如何なる感覚の変化をも受容する観自在な空間である。ただ空白空間はその占有域に限定された形状に従って完結した空間となってそこに充溢する感覚を、ある特定表象形象に結実しようと働き始める。そしてその働きは変幻自在のイメージを追って終わりなく続く想像力の無窮の運動と思われる。かくて白鳥も月も特定でありながら自由に変幻自在する表象形象となった。
時はすべて目前に移りゆく瞬間に化身し、注視は視覚を忘れ融かし、深
まる「生」の実相をそこに感得し始める。画趣の主題はこの白鳥と月に深く関わっていたのである。
「幽玄」は内観世界に表出してくる「生」の実相であり、美感覚の覚醒と集中と結実の過程によって形象化される存在の雅び姿であると云えよう。
「生」そのものに本来形象は無く、仮の形象によってその存在を感得するのみである。人間の形姿もけだし「生」の表象形象に過ぎない。だが「生」の実相は内観の底知れぬ奥より浮かび上がってくる幻像を観続ける視覚に映し出される。幽玄は揺れ動き微妙に変幻しながら美しく結実していく幻像であるに違いない。それは「生」そのものの美の表象である。蛇足は画面上に「生」の幻像を発顕する磁場を創造したのであった。虚の空間、空白の空間は、その美の発顕を促し純粋に自在たらしめる磁場ということが出来よう。
虚の空間は「我が」主体性を純粋に感覚の生として、そこに自らを投じ没する以外に磁場を起動することもなく又、「生」の実相を明かすこともない。
蛇足は自らの「全感覚生」の不思議な旅によって「生」の実相に迫っていったに相異ない。内観宇宙にうごめく「生」の実態は所詮、イマージュを発顕し続ける磁場それ自体であり、その実相は虚空に表出してくる幽玄の美の表象であった。
抒庵